


研究者として幅を持つことが
自己実現につながっていく
成松 宏美コミュニケーション科学基礎研究所
「研究は自己実現と社会貢献の接点に成り立つ」と成松は話す。
充実した研究者キャリアを送るために彼女は何を想い、仕事をしているのだろうか。
一流の研究者をめざして
就職活動をしていた当時、自分の技術で社会に貢献したいという想いを強く持っていました。そして、それが実現できるのは、多彩な研究分野と事業会社を持っているNTT R&Dだと感じ、入社を決意しました。
ただ当初からこのような想いを明確に持っていたわけではありません。自己分析や偉人の伝記を読みふけることで、自身のやりたいこととできることを見つめていった結果、その中心には常に「研究」があったのです。他企業の研究体験型インターンシップに参加した際も非常に興味深く、魅力も感じましたが、自分の軸を見つめた結果として、自分だからできることを追求し、「自分が考えたことをカタチにすることができるNTT R&Dで、一流の研究者となって社会や人々に貢献したい」と想いを持つようになったのです。

期待と課題を常に意識
現在所属している部署では「人に快楽を与えるロボット・エージェントの実現」をめざしています。その中で私は、人のように振る舞えるエージェントの研究に励んでいます。人がどのように相手の発話を理解し対話を行っているかを分析し、その分析結果を応用して「機械としての理解」と「理解に基づく応答」を実現することが私の目標です。
人とコミュニケーションできるロボットは、人に快楽を与えられるだけではなく、一人暮らしのお年寄りの対話トレーニングなどコミュニケーション支援にもつながると考えています。企業での研究は、自己実現と社会貢献の接点に成り立つもの。自らの技術に対して社会からどのようなことが期待され、その実現にはどのような課題があるのかということは、いつも意識するように心がけています。

研究者として複数の軸を持ちたい
入社時はホームネットワークに関する基盤技術の研究、今は対話ロボットの研究に加えて、大学の博士課程に所属し汎用的な現象を数学的に扱う確率モデルの研究を行っています。自分の専門を一つしっかりと持つことも大事です。しかし私は、研究者としての軸を一つだけではなく、常に二つ、三つ持ちたいと思っています。もちろんモデリングの理論自体、さまざまな研究に応用可能ですし、プログラミングスキルもつくので、直接役に立つということもあります。けれどそれ以上に研究者としての幅を持つことが個性となり、自分にしかできないことにつながるのではないかと思うのです。自らの意思でキャリアを切り拓いていけるNTT R&Dは、個性を活かしてもらえる環境だと実感しています。
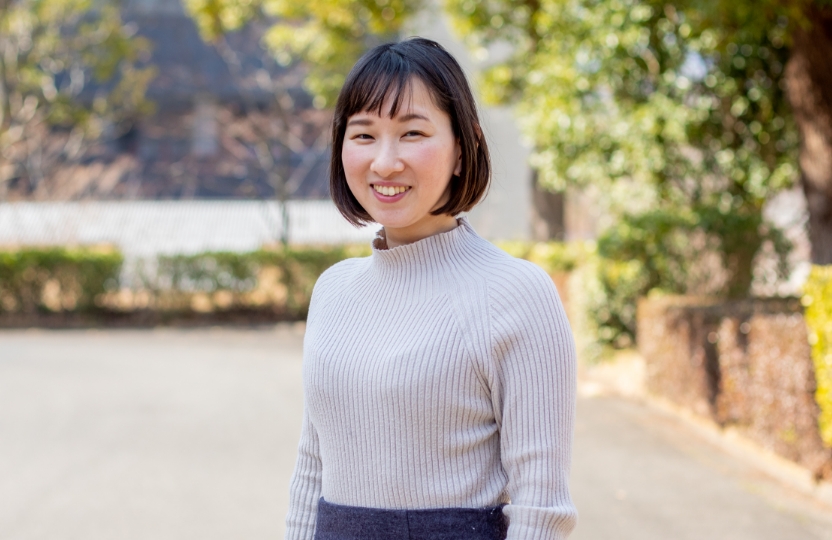
- 成松 宏美
- 2011年入社。マラソンが趣味で、大会で好成績を収めたことも。研究活動も苦しさを乗り越えた先に喜びがある点で、マラソンと似ていると語る。
※記事本文中の研究所名や社員の所属組織などは取材時のものであり、旧研究所名の場合がございます。


